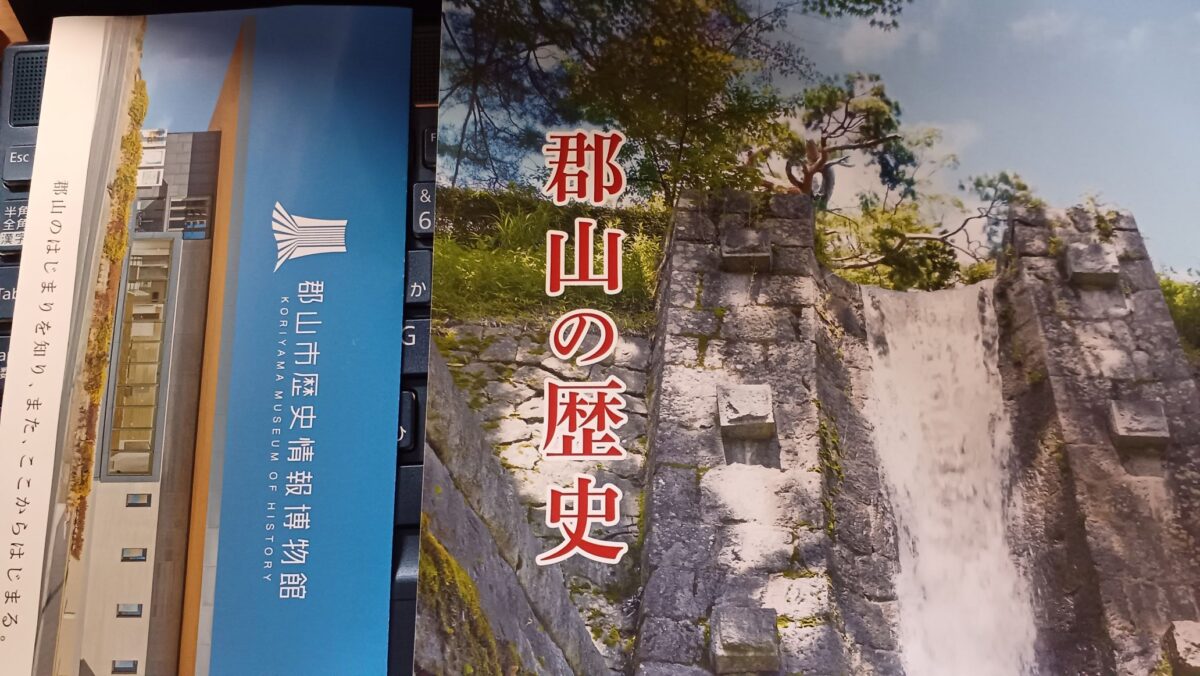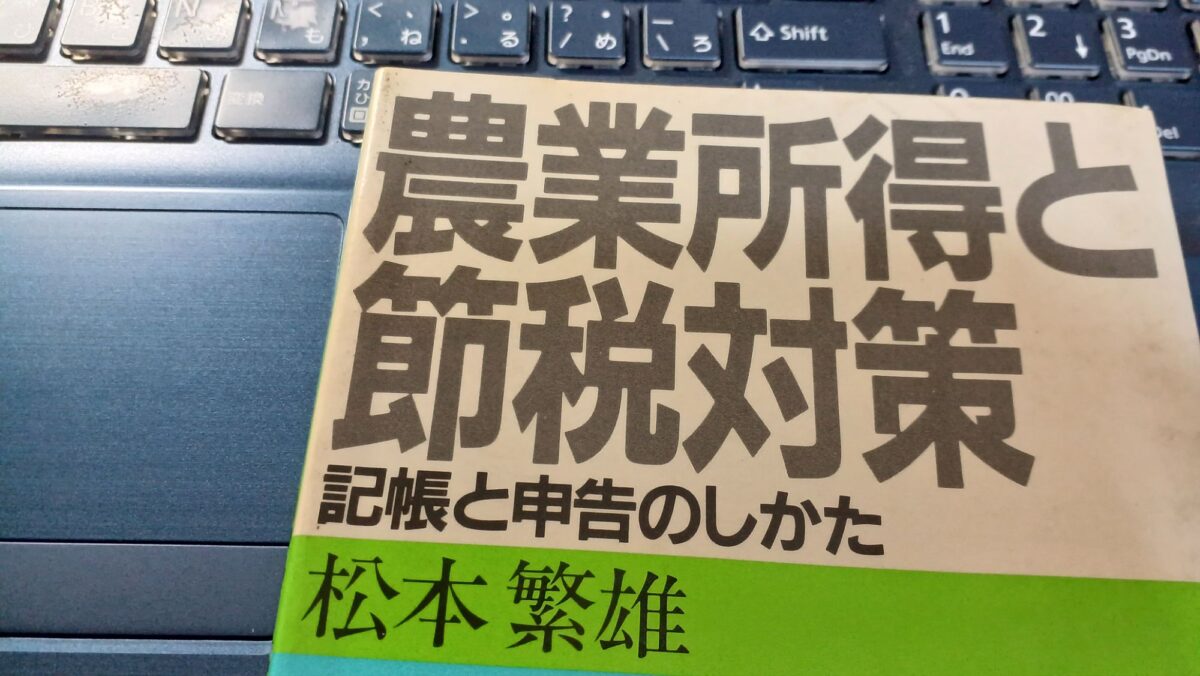2025.10.23(作成日10/31) 福島県の岳温泉に行ってきました~。鉄道とバスで。
月: 2025年10月
猪苗代湖遊覧船に乗ってきました~
2025.10.24 猪苗代湖遊覧船に乗ってきました~。35分くらい、1500円でした。デッキに出たり、船内ガイド音声を聞いたり、写真を撮ったり、楽しかった~♪
郡山の安積開拓 人も農作物も集まらない・・・不運の入植者@明治時代
2025.10.28作成 郡山の明治時代の安積開拓を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!
今回は農業編。
郡山の安積疏水 猪苗代湖の水 郡山の水@明治時代
2025.10.27作成 郡山の明治時代の鉄道事情を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!
今回は水道編。
郡山の郵便・鉄道インフラ@明治時代
2025.10.27作成 郡山の明治時代の鉄道事情を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!
今回は鉄道編。
水郡線・郡山・猪苗代湖ほか2泊3日の旅程表
2025.10.26作成 2025年の秋の鉄道旅、夫を引きずって水郡線を走破してまいりました~。
2泊3日の秋旅、福島県郡山を起点に観光、水郡線で郡山駅から水戸駅まで3時間半、やりました~!やったー!
高市早苗新総理大臣の記者会見、経済対策など聞いた感想
2025.10.21 あんまり政治のニュースに興味ないんだけど、テレビつけたら偶然に高市さんの新総理大臣の記者会見の放送があったので見ました~。
明治後期の本の物価と税金背景を書き留め
2025.10.19 読書の秋!
インターネットで国会図書館デジタルコレクションHPから、明治43年発行の侠客喧嘩屋五郎兵衛を読みました。当時の物価と税金背景を書き留めておきます~。
講談本という存在は、鉱山研究の過程で知ったのです。
読了 講談本 侠客喧嘩屋五郎兵衛
2025.10.17 鉱山研究の秋、読書の秋!国立図書館のデータベースから、インターネットで、明治43年発行の講談本の侠客喧嘩屋五郎兵衛を読みました~。
さすが講談、痛快アクション・人情サクセスストーリーでした!フィクションだそうです。(実在の人物も入れてたりしてる)
故・みなし法人課税と再会
2025.10.16脱稿 9月20日、図書館で、貴重な本に会いました!
夫が見つけて声をかけてくれました。「農業所得と節税対策」記帳と申告のしかた 松本繁雄先生 昭和59年11月発行。
昭和59年???