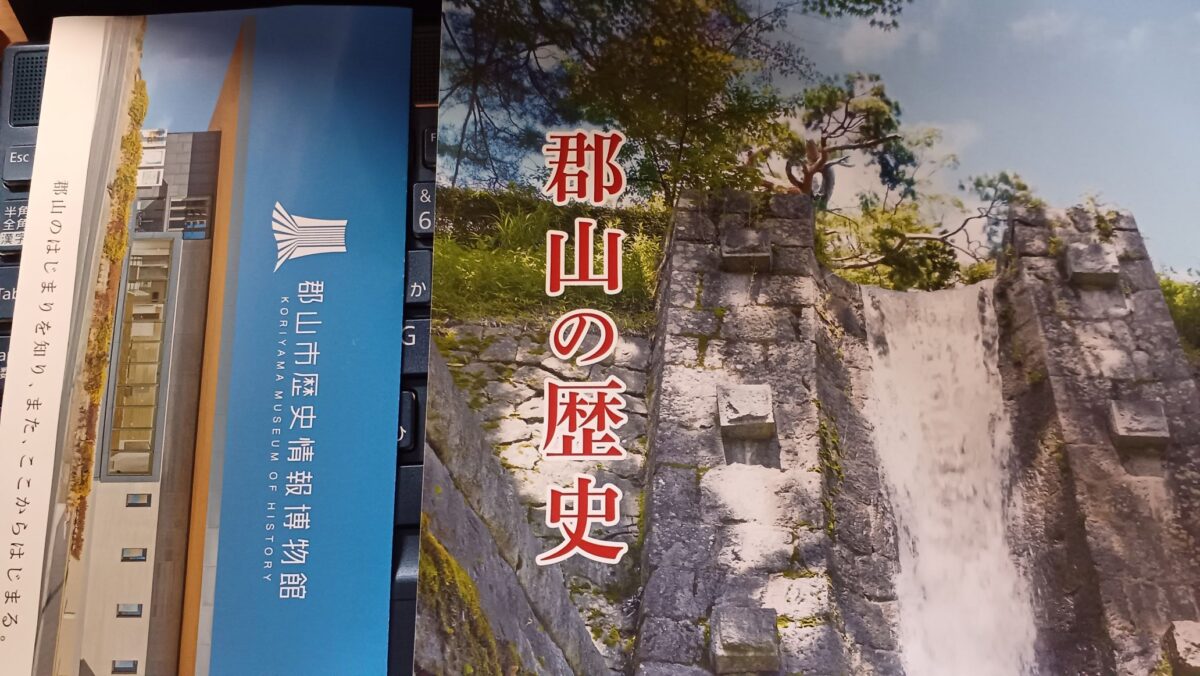2025.10.28作成 郡山の明治時代の安積開拓を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!
今回は農業編。
鉄道編→郡山の郵便・鉄道インフラ@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所
水道編→郡山の安積疏水 猪苗代湖の水 郡山の水@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所
郡山市歴史情報博物館、購入した郡山の歴史の57大槻原開墾と桑野村の誕生以降などが原資料です。
クリックできる目次
サムライ救済の安積開拓
安積地域に水を通す公共事業で経済対策になるし、
新たに開墾して農地にすればもっと農作物を収穫できるし、
失業したサムライを入植させればイイ、
と大久保利通は思ったみたいです。思うようにうまく行かなかったという話を書きます~。
・希望者が少ない。。。
1872年、福島県に赴任した安場さんは、旧二本松藩の士族救済のために政府の政策に沿って大槻原開墾を陳情したけど、当該入植の希望者が少なくてガッカリ。
希望してきたのは200人ポッチリで士族ではなくて農家の次男三男で自力開墾する資金を持ってる人はゼロ・・・・
・資金不足で開成社設立
しょうがないから、主に郡山の有力商人ら25人に呼び掛けて「開成社」を作り事業をはじめて、小作人を募って開墾することになったって。。。。
・地域共同の利用地 入会地でモメ
農道の整備、郵便局や小学校の諸施設も整い、藩政時代には入会秣場(いりあい まぐさば)で郡山・大槻・富田・小原田四カ村の村間の論争が絶えない場所だったので、
境界地をなんとかして(なんとかなったのかな?)1876年には開墾地が桑野村として独立したそう。
入会地モメは、東京の箱根ヶ崎の博物館でもウシコロシ(カマツカ)で境界線を作ったと学びました。
入会秣場
近代化前の農業の肥料は灰が主流だったと「郡山の歴史」32の入会秣場(いりあい まぐさば)と争論で読みまして、
肥料に使うワラなど燃やす材料・保管する近隣村々の農民が互いに入り会う場所が山や原野にあったそうなのです。
薪や草や木を刈り取るとても重要な場所そういうのが秣場(まぐさば)というものだそう。
・水利権問題は合併させて解決?
福島・磐前(いわさき)・若松の3県を合併させて1876年に福島県を設置し、若松県の水利権問題をなんとかしたことと費用面で明治時代に実現することになったそうです。
安積開拓が国営開墾事業に内定
明治維新による士族授産(反乱していたサムライの失業対策、という意味と思います)と殖産興業に力を入れていた大久保利通が明治天皇の東北巡幸の先発として桑野村を視察、その成功に注目した。
この時、中條政恒(旧米沢藩士)から陳情を受け、調査の上、大規模な国営開墾事業を安積地方の原野でGOだ!と内定したそうです。(「郡山の歴史」)
・1882年に安積疏水完成
1879年に安積疏水起工式、1882年にほぼ完成。猪苗代湖の水が安積地方の新田や古田に注がれました~。おめでとう~。
延べ85万人の労力、総額61万円超の経費を要した政府直轄事業でした。
・入植者、地域により格差?
最初の200人の入植者の他にも1878年に500戸の士族が入植、地域により移住入植の事情は異なり、貸与された開拓地の面積や条件も一律ではなかったそうです。・・・・
久留米・高知・鳥取士族が大量入植、岡山・米沢・東京・愛媛士族など。なんか、若松、二本松・棚倉が貸与開拓地が少ない???
若松出身の入植地に恵みの水が届かない??若松・・・・。戊辰戦争と福島事件(1882)があったからかしら。
・入植者、不運なその後
入植者たちの生活は困難でした。
だいたいで書くけど、最初は収穫物が少なくても借りたお金や補助金でなんとか資金繰りをまわしてた。
思うように収穫できず(そりゃそうです、新田だし、教わったところで実際にやったことないんだし、すぐ結果でない)、10年経っても満足な収入がない。
資金繰りに困って開墾せずに日雇い、高利貸しで借金をして肥料代や人夫賃を支払うが土地を手放す者が増加、凶作や水害が追い打ちをかけて1905年(明治38年)とその翌年に大量の転出者が出た。
夜逃げ同然で外国に出稼ぎに行く方もいたという・・・。
自分の拓いた農地の小作人になる人もいたとか・・・・・。
安積郡の小作地率は県内一だったそうで、可哀想に・・・・。
安積開拓があり安積疏水があり、
そこに原野があり、水があり、入会地減って死活問題あり、過去の遺恨あり、ボランティアで労務提供した公共事業があり、割り当て少ないと怒ったり、生産物に感動したり、うまくいかなくて不安になったり、資金繰りに絶望したり、農作業で疲れて眠って太陽を浴びて、ひとり一人の想いが安積の地にあって、郡山の工業化の発達、農業の成功という美しい歴史の裏には苦難があったんだな・・・・。
始めなければ失敗も成功もなかった。
開拓者のご苦労のその後です。現在の郡山のイメージ都会なのに農業がかなり豊富みたいに思えました。若い就農者がこんなにいるんだな~。郡山駅のポスター見て思っただけだけど。
・新規就農
日本の食糧安全保障、どうすればいいんだろうね。
新規就農は、令和の現代でも簡単ではないのでしょう。農地法があるからハードルが高いけど、チャンスはあるよね。自分で食べ物を生産できるってすごいことだなと思います。理論上は、自分は飢えないでしょ。
新規就農時は借入れはするんだけど、安積開拓のように高利貸しに借りてまで種米や人件費をまかなうのは経済的・心理的負担が大きすぎる。
せめて農家さんの自分たちの食糧と最低限の生活だけでも確保できればいいなぁと思います。
宿のテレビで見たけど、農業の補助金については意見が様々あって、要するに耕作放棄地を増やさないための補助金もあるし、私は全部の補助金がダメとは思わないかな。長期間にわたる補助金は本来の制度趣旨とかけ離れて行きやすいし、始めればやめられないんだよね。
農作業を怠けなければ夜逃げしなくて済む農業がいい。(他にもたくさんの話題があるけど別の機会に)
・・・といっても、現在は貧農ばかりではないです。自作農の農業のみで大富豪はほぼいないと思いますが、
自作農の農地があればつつましくならば暮らせる、農閑期や隙間時間のバイト先も何とかある、そういう地方の農家の生活が成立してほしいなと都会しか知らない私は思います。あまい?
都会の人間は店にいつでも食糧があって金で買えると思っている。だから平和がある。

・【寄り道】入植と言えば八郎潟
この安積開拓の苦い経験は、昭和41年の秋田県の八郎潟の入植に多少は生きたように思いたいです。(まぁ八郎潟の入植も思い通りに成功したとは言えないかもね)
秋田の八郎潟は、当時は滋賀県の琵琶湖についで日本で2番目に大きい湖(220km)でしたが、埋め立てられて陸地化したので湖ではなくなりました。それで、福島の猪苗代湖は日本で4番目に大きい湖に昇格したのでした。
日本の湖の大きさトップ4
令和7年の日本の湖の大きさトップ4
1位 琵琶湖 669km
(かつての八郎潟 220km まぁ海だったんですけどね)
2位 霞ヶ浦 168km
3位 サロマ湖 151km
4位 猪苗代湖 103km