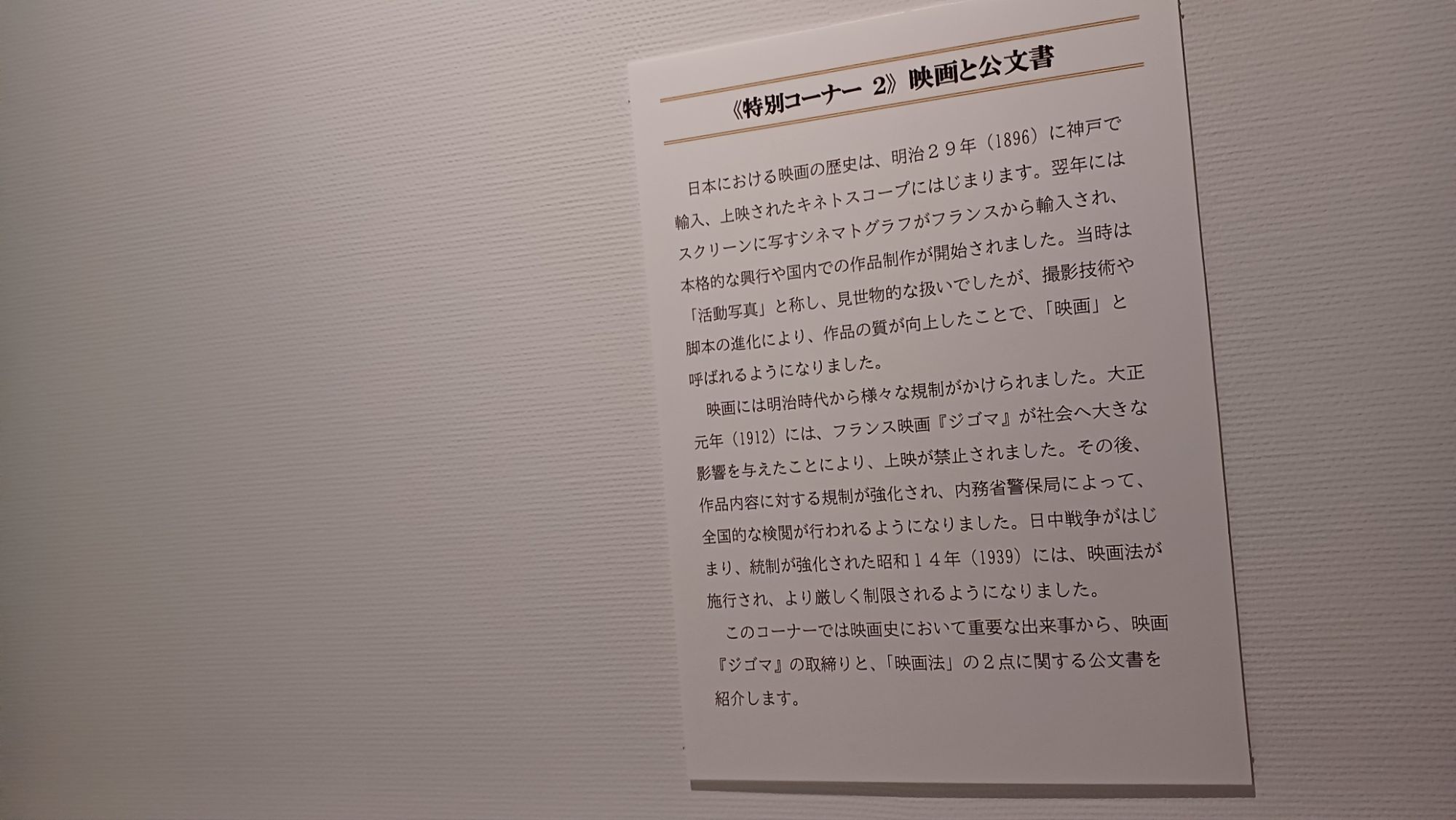2025.11.4 明治時代以後は、日本の歴史がガラリと変わっていくので興味深いです!
郡山市歴史情報博物館、明治時代の講談本、鉱山の劇場、自由民権運動と関連して、演劇の近代史資料を読んだので書いておきます~。
クリックできる目次
・映画と公文書
郡山市歴史情報博物館の企画展で知りましたが、
日本の映画の歴史は、明治29年(1896)に神戸で輸入、上映されたのが始まりなのだそう。
当時は「活動写真」と称し、見世物的な扱いでしたが、撮影技術や脚本の進化により作品の質が向上して「映画」と呼ばれるようになったとあります。
映画には明治時代から様々な規制がかけられました。
ジゴマる
大正元年(1912)には、フランス映画「ジゴマ」が上映禁止に。その後、作品内容に対する規制が強化され、内務省警保局によって全国的な検閲が行われるようになりました。
日中戦争がはじまって、昭和14年(1939)には映画法の施行でより厳しく制限されるようになりました。
「ジゴマ」の取り締まりと「映画法」の資料が展示されてました。
ジゴマは、フランスの怪盗小説をもとに製作された劇映画で、日本に明治44年(1911)に輸入、翌年に全国で大ヒット。
「ジゴマる」という言葉が生まれ、小学生がマネしたようです。
・・・・ジゴマる!現代人でもそういう言葉、あるよね~。なんか親近感(≧▽≦)
映画ジゴマは、犯罪者が主人公の映画で、強盗殺人や放火をするという話だったみたいで・・・・。
当時は喜劇がメインで飽きてた客は、見たことのない内容に殺到したとあります。
バズったんだ。本国のフランスではそんなに流行らなかったみたいで、内容の新鮮味と弁士がよかったのでは、と朝日新聞は評価してました。
※当時の映画は無声だったのか、誰かがその場で話していたみたいです。同時通訳みたいな?
映画法で検閲
昭和14年(1939)の映画法で、検閲の強化、役者やスタッフの登録制度、国策に沿った作品の国民への推奨、があったようです。
16歳未満や女性の深夜労働を原則禁止するなど、子役保護の役割もあったとあります。
映画法は、昭和20年の終戦後に廃止されました。
明治~昭和の演劇の検閲
過去記事で書いたけど、映画より先に演劇で検閲がありました。(出版物が先かも?)
明治後期の本の物価と税金背景を書き留め | 小野寺美奈 税理士事務所
JapaneseHistory_smt_0782-0780.pdf
演劇の場合、明治時代に事前の脚本検閲と、上演中の検閲がありました。
明治期の検閲は、警察が猥褻や残虐性を治安面で取り締まる性質があったみたいです。
地域別に許可不許可が不統一だと演劇業界は徐々に不満に思っていくようです。
1912年(明治45年)の「故郷」という公演が問題視され、それでも明治期の警察側はおおらかでしたが、内務省は社会思想の上演を問題視し、大正期に検閲が厳しくなっていきました、とあります。
全国で統一的な基準を作るならと、厳しい基準に合わせることになってしまったのね。自由民権運動や戦争による思想統一といった時代背景がありました。
思い出すけど、秋田の明治の芝居小屋、康楽館にも検閲者が座るエリアがありました。「えひめの記憶」にも書いてありました。
要点 日本演劇史より
新国立劇場センターが出している、「要点 日本演劇史~明治から現代へ~」ちょっと読んでみます。
演劇界の検閲
演劇業界では、明治5年に「御達し」があり、戦後まで検閲制度が続きました。検閲制度は、思想統制・弾圧手段として使われたと書いてあります。
明治維新前後の日本の演劇
明治11年頃、演劇人の守田勘弥さんほか歌舞伎役者が伊藤博文から、
パリの芝居は高尚で裸になったりしないし道理もつみたるものなり、観客も役者も学識があり、日本の俳優のように玩弄物と思われてないからパリをお手本として日本を改良したい、こんな感じの事を言われました。
当時、活劇物の史実重視の上演は、史実にとらわれて性格の描写が乏しく、芝居としてストーリー展開が面白くなかったみたいです。
私は伊藤博文のコメントで想像するけれど、当時の芝居は、教養とはいえないようなもので、裸もあり、ストーリーは道理が合わず、観客は役者を表現者として見ていなかったのかもしれません。それを芝居といわない気がするんだけど。
江戸時代に思想はいらないし、俗っぽいものが好まれた。昔から今でもカッコイイ・キュートな女優や俳優にウットリしていいと思います。手軽な娯楽も必要!
身近なそれとは別に外国のように教養としての演劇がこの時に生まれたのかなぁ、と思いました。
川上音二郎
川上音二郎さんという方がいて、彼は自由民権運動で投獄されるも言論取り締まりに反抗。知事から演説禁止令が出たので、講釈師→落語家→歌舞伎一座の役者と転向していき、1888年(明治21年)「オッペケペ節」が大ウケしたそうです。
こうして川上音二郎は、「演歌によって民権思想を啓蒙した」とありました。
川上音二郎は一座で渡航。妻は貞奴さん。
一座は、アメリカやパリなどで公演をしました。なんか色々あって。1900年、パリにて、「芸者と武士」(道成寺と鞘当のミックスだ、とある)というタイトルで、血糊を使って切腹、パリの人たちにバズり。
プチト花子
川上音二郎と入れ違いに、プチト花子さん(芸名)という日本人女優がヨーロッパで活躍、ロシアの名優スタニフラフスキーらを夢中にさせたというのです。
彼女は、幼少のころから旅一座で働かされ芸妓に売られるという幾多の辛酸をなめた小柄な女性だったそう。1901年にコペンハーゲンの博覧会に踊り子で出演し、ヨーロッパにとどまった。
劇作家の小山内薫さんは、ロシアのスタニフラフスキーに花子を知っているかと言われ、恥に思ったとありました。日本でまったく無名の単なる踊り子で日本の演劇が評価されてはたまらないと思ったのではないか、とありました。
国内の評価と無関係に、外国で見たこと無いこともあってバズるって今でもありますよね~。ご本人の意に反したようですが、女性版のハラキリで話題になったそうです。逆輸入、とはならなかったみたいです。
プチト花子さんは、彫刻家のロダンに気に入られ、作品になってます。なんか、怒ってる顔の・・・・。旅一座や芸妓でこき使われていた女性が、34歳で外国で脚光を浴びるだなんて、シンデレラストーリーっぽくて、ちょっとワクワクします!(実際にはそんな輝かしいものではなかったみたいですが)
森鴎外が花子について書いた短編小説?(明治43年 三田文学)があるというので、図書館で借りてみました!ほんの10頁だけあり、ロダンと花子の初対面の様子だけありました。
演劇界が発展する1900年代
1900年代に入り、2代目市川左団次や、坪内逍遙(早稲田大学にある演劇博物館の)、小山内薫、自由劇場、築地小劇場など、色んな人や場所の名前が出て来ます。
あんまり分からないからいいや・・・。
社会主義思想の演劇と弾圧
大正9年には「労働劇団」が神戸で出来まして、当時の時代の流れもあって労働者支援・応援のための演劇が上演されるようになりました。「プロレタリア演劇」と呼ばれ、マルクス主義思想(社会主義思想)を基盤とした演劇活動に集約されていく、とあります。
政府の弾圧が厳しく投獄され、検閲も厳しくなり、1933年(昭和8年)には事実上上演が出来ない状態になったそう。1940年には強制解散させられてしまいます。
移動劇団、鉱山等で国策宣伝演劇へ
1940年に発足した大政翼賛会と情報局の肝いりで1941年6月につくられた演劇連盟に加入してかろうじて上演活動を行うことが出来た。
移動劇団は鉱山・工場の産業戦士、農山漁村民、将兵の慰問・激励のために国策宣伝のための娯楽演劇を上演した、とありました。
そうしなければ演劇は出来なかった。
私はこの部分を読んだとき、残念だなぁと思いました。けど、思想の自由も表現の自由もないから、逮捕されちゃう時代では、しょうがないんだね。
風船爆弾
1944年あたりからは18の劇場は閉鎖、東京宝塚劇場は風船爆弾の製造工場に使われました。(たしか登戸研究所にその展示がありました!)
現代は表現の自由
明治維新後、演劇の品性を高めてよと言われ、燃えた役者魂で劇場作っては儲からずに閉鎖、言論統制、検閲、自由民権運動、社会主義思想、弾圧、と時代に翻弄されてきた演劇でした。
戦後、やっと得た表現の自由です。
戦後の昭和時代は演劇がだんだん身近になり、役者に憧れて上京してきた人はいたと思います。私の周りにもいて観劇に行ったし、私は今でも演劇を見るの好きです。
平成の終わりくらいからYouTubeが浸透して、誰でもコストをかけずに動画作成・発信ができるようになりました。コロナがあってインターネットで動画視聴が誰にでも容易になりました。
創作側の表現の自由は大切だなと思います。インターネットでは炎上目的などが出てきて、混沌としている過渡期だけど、昭和初期のような言論統制が正しいとは思わないかな。
観客の批評を見て、やっぱり桐島のあのシーンが良かったってみんな思ってるんだ!だったり、あのセリフ変だった、みたいなのも楽しい♪
今は、国家は検閲をしないけれど、他人同士が暗黙の検閲してるなと思う時があります。自分と違う意見は嬉しくないけど、黙らせようとするのは違うと思います。
創作側も観客側も時代と共に進化して、冷静な批評、表現の自由を守っていきたいなと思います。
インターネットでオプトインというのか、自分と似た考えだけが出てくるから、自分が正しいと思っちゃう。コロナがあって他人に踏み込まなくなる傾向は強まって、自分本位になっても誰も指摘してくれない。
自分が、検閲の時代と同じ偏った視点になっていないかと危惧しちゃいます。
ヨシ、演劇をみて、刺激や影響を受けよう!観劇後、こういう考えがあるのかと帰りの電車で考え込んだり、涙活したり、ただ愉快な気持ちになったり。
またなにか演劇を見に行こう~っと。