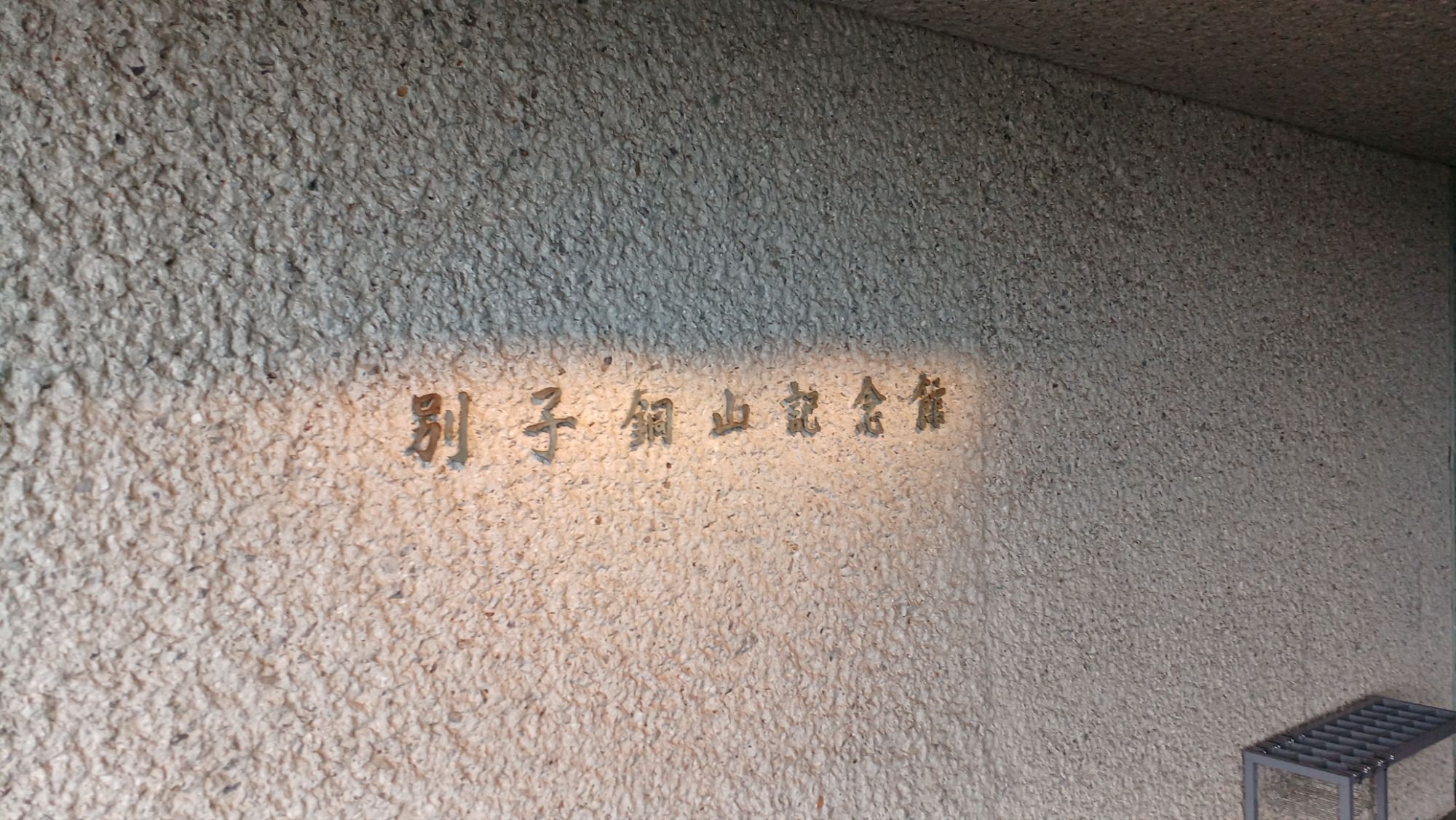2025.8.10 別子銅山記念館、今更だけど、まとめておきます。
2025.4.24に訪問。住友グループが運営している記念館です。学習に行ったので充実!70分ほどいました。時間があればもっといた!
入場無料です。資料販売なし。
クリックできる目次
別子銅山記念館
別子銅山記念館は、1975(昭和50年)開館、大山積神社の境内にあります。
新居浜駅から数少ないバスに乗り、山根グランド停留所で降りたらすぐ。
撮影禁止なので、せっせとメモをして帰って来たけど、HPに書いてあった!けど、現地で時間をにらめっこしながら、少しでも吸収していくんだ!とメモしてきたのは良い思い出になります。
別子銅山は1973年(昭和48年)に閉山し、別子銅山の功績と意義を残すために住友グループにより建設・運営されている記念館です。
283年間、住友のみで運営された別子銅山、世界で唯一の単独運営だったそうです。(他の銅山は、売却等で所有者・運営者が変更している)

・銅の品位
江戸時代は銅の品位が10%超えたほどの品質の高さを誇っていたみたいでした。その後減少、平均で2%ほどになったそうです。
基準が分からないのだけど、すごいのでしょう~。
・坑口
別子山 海抜1000-1300m 1691~明治時代の終わりまで 1.2万人の山奥都市
東平 海抜750m 1916-1930
端出場 現在のマイントピア別子
山の上から掘っていき、少しずつ下がってきたんですね。
・住友家のはじまり
大坂河内出身の「そがりえもん」は、1590年(天正18年)銅吹き・銅細工を家業とする「泉屋」をおこした。
住友初代 政友の義兄。りえもんの長男(?)は政友の養子となって泉屋住友家をおこした。
別子銅山の開坑は吉岡銅山関係者の努力の結果、うみだされたもの。
と私メモがあります。美化しないで正しく記しておくの珍しいよね、イイね。
・別子銅山の発見(歓喜坑)
別子銅山は、吉岡銅山の重鎮 田向重右衛門一行により1690年9月、大露頭の発見に依る。
立川銅山で働いていた渡り鉱夫の切り上り長兵衛が吉岡へもたらした情報により調べ始めたんだそうです。
新居浜駅にあるモニュメント。”すべてはここから、そして未来へ「歓喜坑」”
・17世紀後半の銅の行方
17世紀後半、日本の産銅量は年産6000トンで世界最大。別子銅山は1698年(元禄11年)1500トン産出。日本の1/4国内銅生産量だった。
銅は輸出品の主力、別子銅の多くは長崎貿易でオランダ・中国へ輸出されていた。
・私なりのまとめ年表
別子銅山記念館のHPに年表がありましたが笑。
その場で自分が残したい!と思って書き残したメモを記しておきます。多少間違っているかも・・・笑 そんな大事なこと書き写さなかったんだ、、、な反省も多いです。
1690 別子銅山発見者 切り上り長兵衛
1774 別子山内 疫病流行
1773 享保の飢饉
1784 諸国大飢饉
1836 全国大飢饉
1839 住友家 財政逼迫
1850 計画的植林事業に着手
1851 食糧自給対策として新田開発
1854 近畿大地震
1865 長州征伐
1868(明治1年) 明治維新 王政復古 1869 版籍奉還
1871 廃藩置県 銅の品位が下がっていく
1874 別子銅山 フランス人技師雇用 創業近代化に着手
1890 鉱業条例公布(日本公法廃止)
1893 新居浜に煙害発生
(1894 日清戦争 1894 日清講和成る)
1896 四阪島精錬所建設に着手 1902 第三通洞 東平に選鉱所○○(自分の字が判読不能)
(1904 日露戦争 1905 日露講和成る)
1905 四阪島煙害発生 - 鉱業法公布(鉱業条例廃止)
1907 飯場制度改革に端を発し、金山暴動
1910 四阪島賠償 成立
(1914 第1次世界大戦 1918 ww1終わる)
(1923 関東大震災)
(1931 満州事変)
(1939 第二次世界大戦 1941 太平洋戦争)
1946 別子労働組合 結成 産銅量が激減 別子復興運動始まる
1947 別子労働組合ストライキ 身分制度撤廃問題 坑内大火災(4名死亡)
1950 鉄道電化完成
1965 地圧現象による山なり発生
1973 別子銅山 閉山
・四阪島についての展示
伊庭貞剛(いばていごう・のちの2代目住友総理事)は、(新居浜の)煙害対策のため、新居浜から20キロ先の無人島・四阪島(しさかじま)に銅の製錬所を移転。
1905 四阪島の操業開始。ガス排出が継続された。 1939 煙害問題 終止符。
四阪島には最盛期は5500人が暮らした。
(参考で、マイントピア内の風呂事情展示によると、うどん屋が出来たねっこ町では1万人の人口を越えたようでした)
昭和46年、新たに完成した東平製錬所に移管、四阪島は1977(昭和52年)に幕を閉じた。

大山積神社に、四阪島の煙突のモニュメントと碑があります。
「亜硫酸 吐きし煙の 無くなりて 島はよみがへる 人も草木も」
第16代住友吉右衛門
煙害のために奔走した伊庭貞剛、住友がどう住民に向き合ったかは、この後、日暮別邸記念館で勉強してきました!
・銅山札(お金)
山銀札(やまぎんさつ)とも呼ばれたみたいでした。
明治2年、山内限りの通用金券があった。
明治6年~明治9年 労働量を表示した金券(歩役札 ぶやくふだ)
紙幣類似の為、廃止になった。
・友子と鉱夫取立状
「友子」とは、友子同盟などとも呼ばれる採鉱夫の自治的組織のことだそうです。
坑内で鉱石を採掘する鉱夫(採鉱夫)になるには、まず見習いとして親方のもので修行を積む必要があった。(まぁ、そうだよね。税理士業界も同じ)
一人前になると友子の一員となることが認められた。この友子の一員になるための方式に則った儀式「取立所(とりたてしょ)」その際に交わされる書面を「取立状(とりたてじょう)」と言ったそうです。(日立でみた気がする)
取立所に、鉱夫として働くための資格説明書のようなものであり、本人と親方の名前と共に証人として多くの関係者の名前が列記され巻物等に成形されて本人にあげたみたいです。
友子は、鉱山ごとに組織され病気やケガなど働けなくなった時に見舞金を支給するなど互助会的な性格もあった。
また、全国的な共通性・繋がりなどがあり、それぞれ友子は、取立状を持つ者が他の鉱山に入ろうと(移ろうと?自分の字が判読できず)来山したときなどに、友子の一員として便宜を与えた。
江戸時代から組織され、明治期に発展したが、労使関係の変質などにより衰退し、昭和10年代にはほぼ自然消滅した。
別子銅山で行われた最後の取立は1972。(1973年に閉山だから、書き写し間違いかも?)
・鉱夫取立状
徳川家康制定といわれる山例53条を基とし、江戸時代末期より組織された「友子組合」友子同盟等の鉱夫共済精神が盛り込まれた取立式は古式により実施、後日、個人への免状が公布された。
・別子山から四阪島へ
新居浜駅には鉱山についてのモニュメントがたくさんありました。
住友グループの始まりでもあり、住友と共に続いていく町なんだろうなぁ~。
さて、この後、広瀬歴史記念館→日暮別邸記念館と、ガッツリ別子銅山を勉強します~。