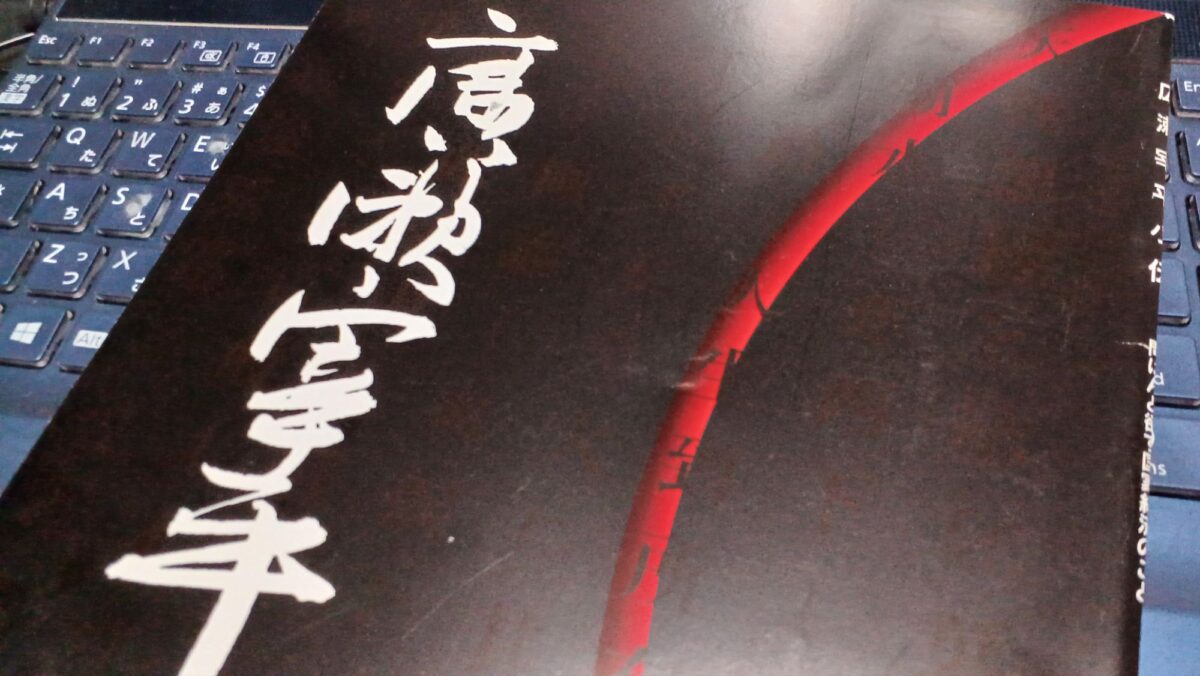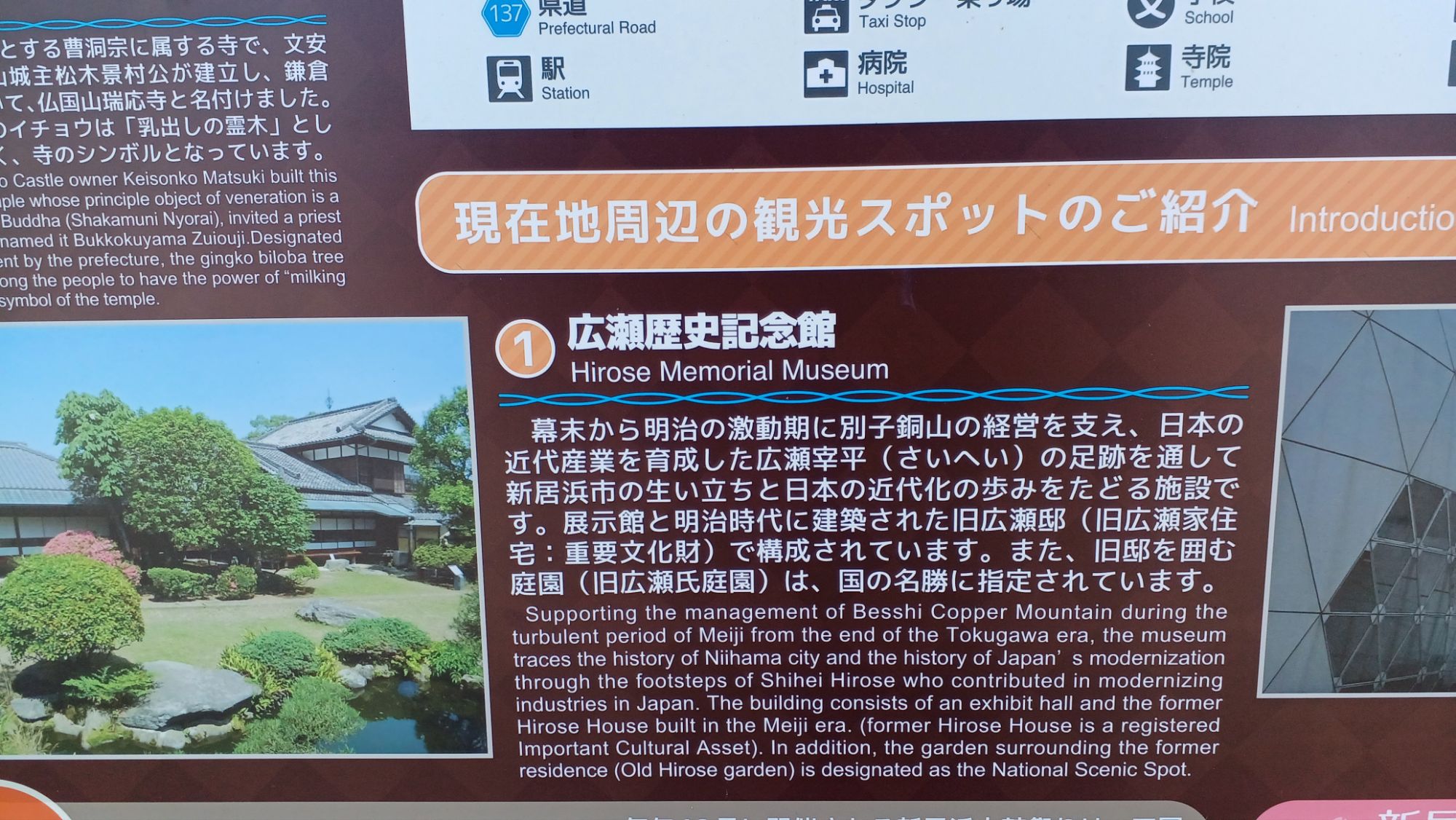2025.8.13 愛媛県にある別子銅山の広瀬歴史記念館に2025年4月24日に行ってきました!いまごろまとめ。
住友グループに創業者?広瀬宰平さんの記念館。偉人伝的な記念館ですが、別子銅山のことがよく分かります。自分のメモを書いておきます!なんと邸宅も含めて2時間30分もいました!
正式情報は、住友グループのホームページで確認してください~。
広瀬宰平 その1 | 住友の歴史 | 住友グループ広報委員会
広瀬宰平さんは、名前を変えたのだけれども、便宜上、最初からず~っと広瀬宰平(敬称略)、と書きました。
クリックできる目次
おおまかな宰平さん年表
広瀬宰平さんは1828(文政11年)は、滋賀県のお医者さん宅の次男として生まれる。9歳の時、叔父に伴われて別子銅山へ。11歳で勤務し28歳で広瀬家へ夫婦で養子になる。38歳で別子銅山の支配人に就任。
1868(宰平さん41歳)別子銅山の差し押さえ(?)回避。
1869自家田畑を抵当に。山銀札を発行。
1876(宰平さん49歳)別子銅山を近代化へ。翌年、住友家総代理人へ就任。
1891(宰平さん64歳)別子銅山鉄道敷設に着手。
67歳で依願退職(87歳で亡くなる)
*****
明治維新前、土佐藩から別子銅山を取り上げられそうになった際、広瀬宰平は、(明治1年、慶応4年)徳川家から明治政府への乗り換えを決め、川田小一郎(当時は川田もとえもん。後の日銀総裁)に賭けてみることにした。
第3代総裁:川田小一郎(かわだこいちろう) : 日本銀行 Bank of Japan
旧大名貸付18万両と買請米(鉱山夫の米代金)約9万両があり、回収と支払いに奔走した。
(住友からの)別子銅山売却に反対し、産業資本未発達なのでインフラ整備をして輸入で儲ければ国益になる、と説得をした。
別子銅山の売却を阻止
住友家 初代政友は、京都で薬・出版を営む。
2代友以は1623(天和9年)大阪へ進出。屋号を泉屋に。
1690年、別子銅山発見される。
幕末期には産銅のコストアップに悩まされ、1843年(天保14年)には、休山願を幕府に提出するほど、経営に苦しんでいた。(マイントピア別子併設の道の駅2階でテレビ映像が流れてました!)
広瀬宰平がやっとの思いで土佐藩から別子銅山を住友家に残しておくことに出来たけれども、大阪本店の重役からは経営難だから売却しようと言われる。大事なのは住友のイエじゃないんだ、と阻止!
その2年前、1866(慶応2年)は、大みそかに勘定奉行へ鉱山稼ぎ人の食糧米を嘆願に行き、鉱夫たち5000人の命がかかっている!とうったえた漢詩が残っているそうです。

熱血!広瀬宰平
別子鉱山職員等級布告書
文明開化、能力主義を唱える広瀬宰平。年功序列で無能年寄り(!)への宣戦布告でした。封建制が根強い時代にコレ言えちゃうのがスゴイですね。
(広瀬宰平は、住友家の親類ではありません。こういうの言えちゃうし受け入れる住友家だったみたいです。)
土佐藩預り所宛ての別子銅山稼行願
土佐藩へ、200年も続いた住友(名前?自分メモが判読できない)がずっとしているから存続したい、と書いた。川田は良いと思ったようだった。広瀬宰平の山への強い想いが若い川田の心を動かしたようでした。
土佐が支配したら鉱夫が不安になって暴動がおこると言い、鉱夫らが路頭に迷わせたら良いこと無いと川田は言う。川田は、(土佐藩のことだけ考えることじゃなく国全体を考えた)一流の武士でしかなかった。
岩倉具視書状
別子銅山の近代化を言う広瀬宰平。岩倉具視は明治8年8月の広瀬宰平への手紙に私利私欲に走らずに国益を考える感謝を書いている。
広瀬宰平の志、政府の役人でもないのに国益のために近代化を説いたことを岩倉具視を感服させた。

お金、販路、水道、物流
開拓資金
明治3年(1870)、広瀬宰平は大阪為替会社から、別子銅山近代化の開拓資金として2万両を借りた。住友家が大阪為替会社に出資してたので、借りることができたみたいです。
山銀札、歩役札
山銀札は、明治2年(1869)9月、別子銅山の金融緩和の為、広瀬宰平が自家の田畑を抵当に発行した。
私札のため、裏面に広瀬宰平の署名をした。山銀札70匁が1両に相当。
1両=1円=当時の蕎麦200杯分(令和7年8月はお蕎麦1杯500円とすると10万円くらいでしょうか)
歩役札は、明治6年(1873)8月~明治9年5月まで使った。私札が禁止されたため、使ったようでした。
私札がまた出てきた。三池炭鉱、ハンセン病資料館でも見たわね。
貿易事情の変化
資料によると、幕府から長崎輸出銅をすべて買い上げてもらっていたけれども、明治2年に明治政府は銅の自由販売を通知、住友家は自力で外国に販売して鉱山夫米も自力調達することになりました。
明治4年から神戸出店して外国商館へ売り込みをした。とあります。
この後、産出銅量がとても増えたので、かなり儲かったと思います。設備投資も運転資金も販路も金額も自分でするようになったってことよね。
日本坑法 制定される
日本坑法が明治6年7月20日(1893)制定されました。
日本坑法は鉱山法令で、日本で最初の(鉱山の?)体系的な法律が出来た。鉱山は政府の○○(自分のメモが判読できない)、本国人主義。日本人が鉱山経営をする。(と、自分メモしてある)
第2条に、全ての鉱物は政府の所有であると書いてある。鉱業専有主義。
第4条に、日本国籍がなければ、鉱山経営できないとする。本国人主義。
鉱区の制定や鉱業区権もはじめて制定された。こういう主旨だったようです。
富鉱帯をもう一度
安政1年(1854)に大地震で水没した別子銅山の三角の富鉱帯があった。
明治9年(1876)東延斜坑を作った。
明治27年(1894)、三角(みすま)の富鉱帯がもう一度!
大地震で水没した三角の富鉱帯が、40年ぶりに宝の山に辿り着き、広瀬宰平は夢をかなえる。
小足谷疎水道
小足谷疎水道(こあしだにそすいどう)が完成したのは明治19年(1886)12月。
1792(宝政4年)小足谷から坑内の○○(自分メモ判読不能)坑まで排水坑開さく着手したが、吉野川への銅水流出を恐れて徳川藩の反対で中断していた。
明治1年(1868)に広瀬宰平によって再開、明治19年に小足谷疎水道が竣工した。
(隣の徳島県に排水、県境が近いのですが、なんか手腕すごいね。)
国内初の鉱山山岳鉄道の敷設
海抜1300メートル、仲持ち(運搬夫)に限界を感じていた広瀬宰平。
(自分はカゴに乗って移動していたのに)
明治維新後に牛車道を作る広瀬宰平。銅山峰を越えて新居浜までの道を作る。
資料によると、運搬夫の多くが解雇され、恨みをかったようです。
さらに、銅山峰の直下にトンネルをはり、我が国初の鉱山山岳鉄道を敷設。
広瀬宰平は、明治22年(1889)6月に北米ロッキー山脈の山岳鉄道を見て、我が国最初の本格的な山岳鉱山鉄道ができた。明治26年3月に下部鉄道(惣開~端出場の10km)、明治26年8月に日本初の上部鉄道(海抜1000メートルの石ケ山丈~角石原の5.5km)を作った。
近代化による運搬量の変化
仲持ち俵1個 → 牛車で8.5個 → 別子鉱山鉄道で520個
広瀬宰平の植林
明治20年、広瀬宰平の鉱山職員への演説では、
別子銅山職員には目的がある。本来の目的を思い出し、初心を思い出して勤勉・節約・倹約、繁栄の基礎だ。
輸出しているし日本を潤しているから頑張ろう、と言った。
*****
「百年の謀は徳を積むためにあり、十年の謀は木を植えることにあり」として別子銅山の植林を開始した。
謀=はかりごと

学びになりました
広瀬宰平さん、全体や先見の明があった方なのねぇ~。広瀬宰平さんの偉業を記録する記念館なのだから、ワンマンぶりだったりミスはほとんど書いてないです。
けど、立派な方だったんだなぁ~と私は思う。いいなと思うところを沢山吸収できたと思う!