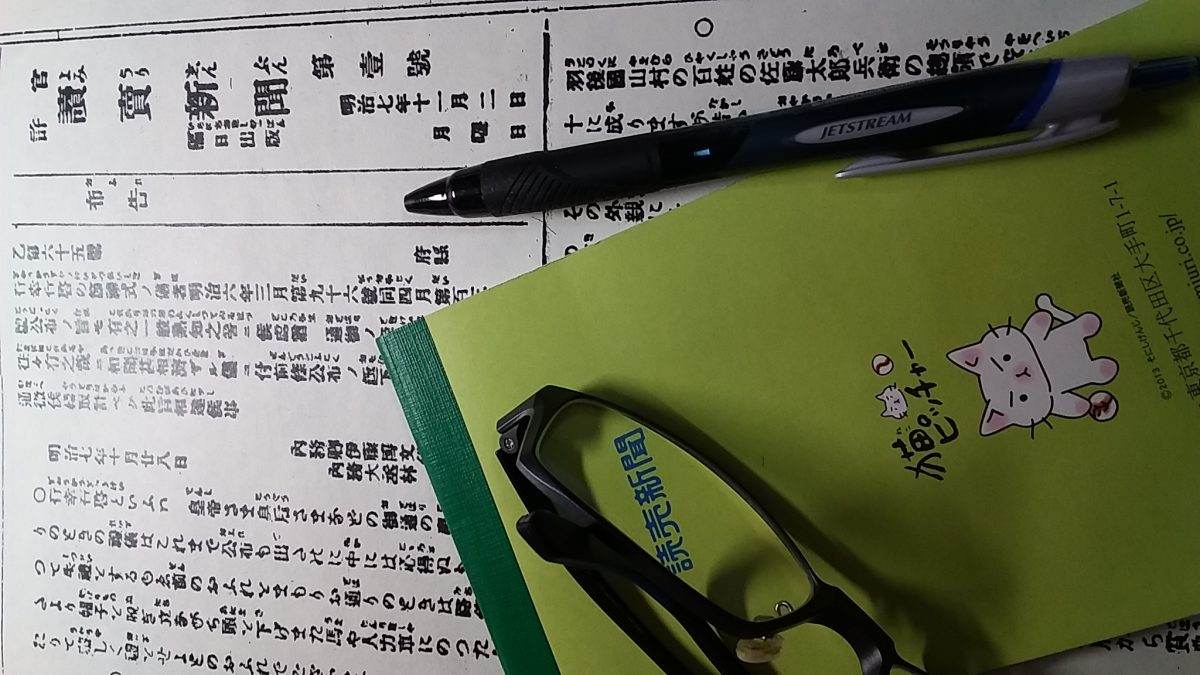取材のポイントを、新聞屋さんからもらったメモから学ぼう。
税理士ってどうあるべき?靴底をすり減らし、納税者の話を熱心に聞いてよく考えればいいんじゃないか。
取材のこころえ より。
1、ネタを探す(現場力)
いつもアンテナを張ろう!テレビ新聞市町村の広報誌など。でも一番すごいネタは身の回りの出来事!
近所ネタは自分が当事者でもあるし現場を見てるもんね。
顧客回りした時には、帰り道にお客さんがよく買い物してるお店を見つけると、動線が分かって会話が広がり、情報量が増えるので私は現場主義でやりたい。
2、取材(ヒアリング力)
まずは挨拶と自己紹介を。取材中はメモを取って、分からないことはその場で質問する。人名や電話番号は間違えないように!
お名前や誕生日、住所に電話番号は、本人にとってはお馴染みだけど、税額に無関係なことが多く、税理士が覚えておくことではない(むしろ、個人情報だからあんまり覚えておくものでもないと思う)。
チェックの重要度もどうしても後回しにしてしまい間違えやすいよね。こういうの、間違えてても納税者の方が遠慮してなのか我慢してしまい、税理士に対する不満が蓄積するケースが多い気がする。
最後はご本人にしっかりチェックしてもらうといいよね。
分からないことは、私はなるべくその場で聞く派。アホと思われてもいい。
適当に話を合わせずに、質問したことで分かったことがある。むしろ、スルーしてたら危なかった案件もあったり。知ったつもりや、やり過ごしは、結構危ないよね。その人のキャラクター性もあるけど、お互いの認識の一致のための確認はすべきだよ。
3、記事を書く(探求力)
記事は、手短で分かりやすく。いつ、どこで、だれが、何を、どんな風に、なぜ、ということを考えながら書く。最後に取材メモを見て間違いがないか、チェック!
「なぜ」その答えが返ってきたのかを考えると、相手のことをもっと知りたいと思うようになる。きっとこうだから、という思い込みに注意せねば。
納税者の気持ちに寄り添うことは大事だよね。でも、経費にならんものは、経費にならない。感情とルールは違う。
こういう日記やブログは、自分がなぜ書こうと思ったのか?を考えるとおもしろい。書き上げてから書く動機に気が付いたりする。
人の話をよく聞き、理解して、ほかの人に正確に伝えることは、学校でも社会に出てからも必ず役に立つよ。
ほんとだよね。当たり前だな、と思うけど、全然できてないや・・・。
そう考えると、ヒアリング力が税理士の能力といえるかもしれない。たくさん税法を知っていても、話してもらえなけば適用の有無にすら辿り着かないもん。
税法の勉強もするし、質問力も磨かねば。…そんなに一気にたくさんは出来ないから、ちょっとずつ頑張る!
4、見出し(伝える力)
見出しには読者に記事の大まかな内容を簡単に伝えて読みやすくする役割があるよ。見出しは7文字から10文字くらいがいいといわれてて、漢字とひらがなをバランスよく組み合わせるのがいいみたい。
新聞は情報が多すぎて全部読む時間がとれないこともあるけど、見出しだけで分かるようになってる、とは聞くよね。数文字で表現するってところが、俳句と通じていてセンスが問われる?
相手に伝えるときには、なるべく分かりやすく短くと思うんだけど、これが何年たってもなかなか上達しない。同じ話しても人によって受け止め方が違うから、使いまわしができないよね。オーダーメイドしないと。
5、写真(見せる力)
写真やイラスト、表をいれることは、記事と同じくらい大事な情報。分かりやすい誌面作りを心がけよう!
イラストは、「いらすとや」で検索するけど、ないときは自分で書こうかな。絵心のなさが評判の「アホ絵」(夫命名)を増やしていこう。
データは、ありすぎると、かえって分かりづらくなってしまう。前期比較、3期比較、5期比較、利益率、原価率、その他色々、上げればきりがない。説明しても見てもらえない時があるよね。
せっかく用意したものを捨てるのは残念だけど、間引きも必要だよね。ほんと、切ない。ボツにして削除した文章が結構あって、まだ成仏せず残っている。うぅ・・・
6、まとめ
記者の取材のこころえを、さらりと読んだとき、これは税理士にも通じるなぁと思ったんだよね。
当事者にしか分かりえないことが絶対にあって、どこまでも把握できるわけではないもんね、私の人生ではないから。
ふと漏れたお客さんの一言から税額が動いたこともあった。どうして話してくれなかったというと、どうして質問しなかったと言われた。
相手がある仕事は難しく、おもしろい。